精神保健福祉資料とは オープンデータの特徴や活用方法を解説
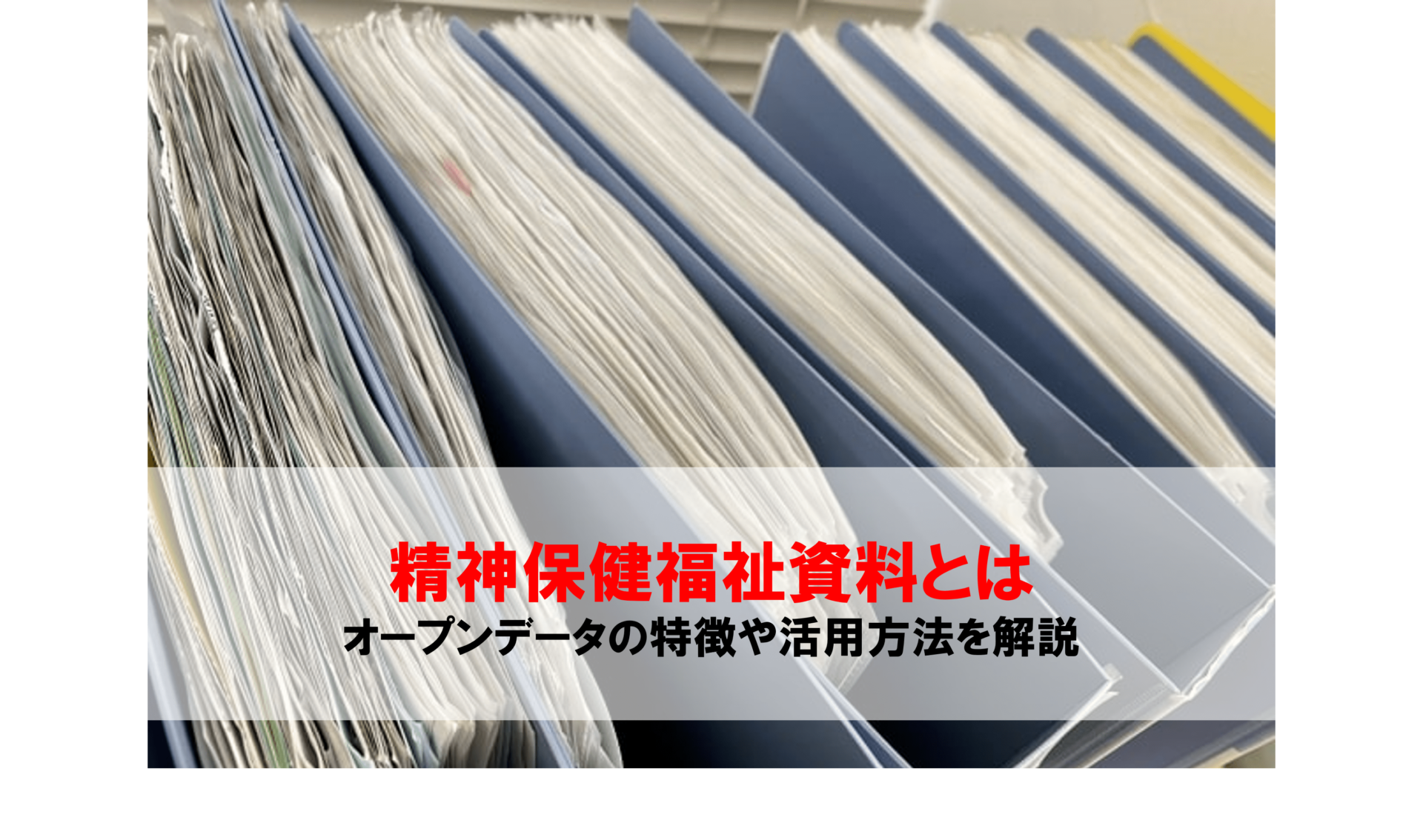
日本において、精神疾患を有する患者数は年々増加傾向にあります。また、日本人は精神科やカウンセラーの受診を躊躇する性質が強いことから、数字として表れていない患者も多いと言われています。その背景には、IT技術の発展に伴う睡眠障害の増加や社会的孤立、競争社会などが影響していると言えるでしょう。
厚生労働省は、精神科病院、精神科診療所、および訪問看護ステーションを利用する患者の実態を把握するために、精神保健福祉資料を公開しています。
この記事では、精神保健福祉資料のオープンデータの活用を検討している企業担当者に向けて、オープンデータの特徴や活用方法を解説します。
精神保健福祉資料とは
精神保健福祉資料とは、精神保健医療福祉の提供体制構築を目指したモニタリング調査等の結果をもとに作成した資料です。
「医療計画指標データ(NDB、各種データソース )」と「630調査集計データ」に大別して、厚生労働省の各種補助金による研究班が調査・集計・公表しています。
本記事では「630調査」に関して、令和4年度のデータに基づき詳しく説明していきます。
630調査とは
毎年6月30日付で、自治体と、全国の精神科病院や精神科診療所などの医療機関、および訪問看護ステーションにおける精神保健医療福祉の現況モニタリングを行う調査です。
630調査では、以下のような施設に対して調査を行っています。
|
調査対象施設 |
定義 |
| 自治体 | 47都道府県および20政令指定都市の主管課 |
| 医療機関 | 下記条件に該当する医療機関 ・令和4年6月30日時点 で医療法上の許可・届出を行っている ・地方厚生局への届出を行っている医療機関番号を持つ ・「精神科」又または 「心療内科」の診療を行っていることを都道府県・政令指定都市の精神保健福祉主管課が把握している |
| 訪問看護ステーション | 全国全ての訪問看護ステーション |
調査概要は、以下の通りです。
①自治体調査
- 医療機関・訪問看護ステーション数、医療圏の数等
- 非同意入院の「入院届」「退院届」
- 精神医療審査会機能
- 精神障害者保健福祉手帳の交付状況
②医療機関調査
- 各医療機関機能および職員、病棟機能、拠点機能
- 在院患者の状況
- 退院患者の状況
- 医療保護入院患者の状況
- 訪問看護機能
- 退院後生活環境相談員の状況
- 精神科の外来診療およびリエゾン診療の実施状況
③訪問看護ステーション調査
- 利用者数、各種加算算定の有無、スタッフの内訳
- 各種届出状況
![]() 関連記事もぜひ参考にしてみてください
関連記事もぜひ参考にしてみてください
◆地方自治体における医療オープンデータの取り組み状況は?公開データも紹介
◆福祉に関するオープンデータのご紹介
精神保健福祉資料のオープンデータの内容

精神保健福祉資料として公表されているデータのうち、「630調査集計データ」について詳しく説明します。平成28年以前のフォーマットで集計された下記の項目の他に、「精神科医療機能の概要」「在院患者に関するクロス集計」「退院者に関するクロス集計」に関する内容が公開されています。
|
集計単位 |
大項目 |
小項目 |
|
全国 |
精神科病院の状況 | ・病院数・病床数・病棟数・休床中病棟数 ・入院料等の届出状況_病院種別毎の病院数、病棟数、病床数 |
| ・病院数・病床数・病棟数・休床中病棟数 ・入院料等の届出状況_病院種別毎の病院数、病棟数、病床数 |
下記条件の総数、病院種別毎 ー疾患分類×年齢階級・入院形態×性 ー入院形態×年齢階級×在院期間 ー開放区分・入院料等の届出状況×年齢階級・在院期間 |
|
| 医療観察法指定入院医療機関の状況 | 下記条件の医療観察法病棟の対象者数、病院種別毎 ー疾患分類×年齢階級×性 |
|
|
都道府県 |
精神科病院の状況 | ・精神科病院の概況 ・病床数・病棟数 ・入院料等の届出状況(病院数、病棟数、病床数) |
| 精神科病院在院患者の状況 | 下記条件の在院患者数 ー年齢階級・入院形態×性 ー疾患分類 ー入院料等の届出状況別 ー入院期間×住所地・施設所在地×年齢 |
|
| 認知症治療病棟の状況 | 在院期間別の在院患者数 |
精神保健福祉資料の活用方法

精神保健福祉資料におけるのオープンデータ は、地域の精神科病棟にかかる医療状況を把握でき、開業医に向けた開設地域の特定や自社商品のターゲット層の選定などに活用できます。主な活用方法は次の通りです。
開業医に向けた医療過疎地域情報の提供
精神保健福祉資料のオープンデータ等に基づいて作成された地域精神医療資源分析データベースが「ReMHRAD」です。
ReMHRADでは、以下のような情報が都道府県・二次医療圏・市区町村別に表示されます。
● 精神保健福祉資料における指標の状況
● 精神科病院に入院している方の状況
● 訪問看護ステーション・各福祉サービスの事業所の多寡
● 各社会資源の位置情報
ReMHRADを活用することにより、全国の各地域における精神科病棟の入院患者状況や地域の精神疾患に関する各種診療行為の算定患者数が把握できます。入院患者や精神疾患で診療を受ける患者数が多い地域、すなわち精神科病棟の需要が高く、医療機関を拡充すべき地域(医療過疎地域)が特定できるのです。
医療過疎地域の情報を精神病院の開業を検討している医師に向けて提供することで、日本の医療課題である医療需要に見合った医療体制の充実にも貢献できるでしょう。
精神疾患患者向けサービスのターゲット選定
精神保健福祉資料のオープンデータを活用することで、各精神疾患の治療に役立つ自社サービスのターゲット層を選定できます。当データでは、精神疾患ごとの入院患者数が年齢階級・性別ごとに集計されています。
そのため、自社で取り扱っているサービスの需要が高い年齢層や性別が特定でき、ターゲット層に適した方法で集客が可能です。例えば、アルコールによる精神障害を患っている患者に向けた講座を開催している企業や書籍を出版している企業の場合、アルコールによる精神障害で入院している患者が最も多いのは、40歳以上65歳未満の男性です。
40歳以上65歳未満の男性といえば、管理職に就き、現場の責任を取るために出社している方も多いと思います。通勤中の電車内に広告を出すことで、需要の高いターゲット層の目に止まりやすい状況を作り出せ、商品への問い合わせ増加が見込めるでしょう。
まとめ
精神保健福祉資料のオープンデータには、精神科病院の施設や患者に関する状況が集計されています。
ぜひ精神保健福祉資料のオープンデータを活用し、精神病院の開業先に相応しい医療過疎地域や自社サービスの需要が高いターゲット層の特定に役立ててみてください。
<医療系オープンデータ>
弊社では医療系オープンデータをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!
>>セミナー一覧はこちら
また、弊社では活用しやすいよう加工した【DPCデータ】や【病床機能報告データ】を提供しています。こちらもお気軽にお問い合わせください。
>>DPCデータ提供サービスについてはこちら
>>病床機能報告データ提供サービスについてはこちら
全国の医療機関(医科・歯科・薬局)マスタを無料または有料で提供いたします。
>>医療機関マスタの詳細こちら!
>>医療機関マスタ提供に関するQ&Aはこちら

