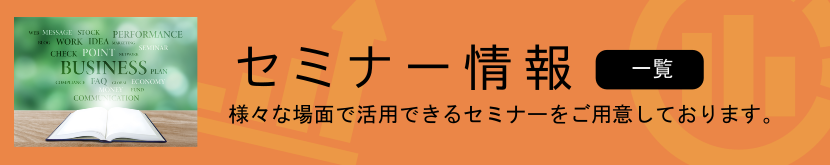Marketing Cloudのマルチアカウント管理とは ブランド統合や運用設計を分かりやすく解説
#Marketing Cloud #運用 #マルチアカウント #管理

目次
- 1. Marketing Cloudのマルチアカウント管理で押さえる3つの基本
- 1.1 アカウントとBusiness Unitの関係
- 1.2 Multi-Org構成の考え方
- 1.3 データ統合に欠かせないShared Data Extensions
- 2. ブランド統合で変わる3つの運用設計ポイント
- 2.1 権限・ガバナンス設計の重要性
- 2.2 配信フロー標準化による効率化
- 2.3 データ基盤の一元化と横断分析
- 3. マルチアカウント統合に取り組む際の3つの選択肢
- 3.1 単一Org+複数Business Unitによる統合
- 3.2 Multi-Org構成による柔軟な分散管理
- 3.3 ハイブリッド型での段階的統合
- 4. 統合設計を成功に導く3つのステップ
- 4.1 現状アカウントの棚卸しと課題把握
- 4.2 運用ルールとデータ設計の合意形成
- 4.3 導入後の評価指標と改善サイクル
- 5. まとめ
Marketing Cloudを複数ブランドや事業部で導入すると、アカウントやデータが分散しやすくなります。その結果、顧客体験の統一や成果の横断管理が難しくなるのが現実です。
本記事では、マルチアカウント管理の基本からブランド統合の設計ポイント、さらに成功へ導くステップまでを整理し、統合責任者が意思決定に役立てられる知識を解説します。
Marketing Cloudのマルチアカウント管理で押さえる3つの基本
複数ブランドや事業部を抱える企業がMarketing Cloudを導入すると、最初に悩むのが「アカウントの構造をどう設計するか」という点です。ここを安易に決めてしまうと、後から「データが連携できない」「権限が複雑すぎて管理が回らない」といった問題に直面します。
統合責任者にとっては、基盤の設計が全体最適につながるかどうかの分かれ目といえるでしょう。そこでまず確認しておきたいのが、次の3つの基本です。
アカウントとBusiness Unitの関係
Marketing Cloudでは、一つのアカウントの中に複数のBusiness Unit(BU)を設定できます。たとえば「食品事業部」「化粧品ブランド」「子会社A」と分ければ、それぞれのチームが独立して運用できる一方、共通の基盤は保てる仕組みです。
この柔軟性は魅力ですが、BUが10以上に増えると管理は一気に煩雑になります。ユーザー権限だけで数百パターンを超えるケースも珍しくなく、担当者の入れ替わりで混乱する企業も多いのが現実です。
だからこそ、「どこまでを分け、どこを共通化するか」を最初に決めておくことが、後の混乱を防ぐ近道になります。
Multi-Org構成の考え方
各事業部や地域が別々のSalesforce Orgを使っている企業では、それぞれをMarketing Cloudに接続する「Multi-Org構成」が選ばれることもあります。海外拠点や子会社が独立して運営している場合には有効な方法です。
メリットは、組織の自律性を保ちながら運用できること。一方で、データの重複や整合性チェックといった手間は確実に増えます。特に5つ以上のBUを同じユーザーに接続すると品質が低下するという制約もあり、規模が大きくなるほど注意が必要です。
自社にとって本当にMulti-Orgが妥当なのか、経営判断として一度立ち止まって検討する余地があるでしょう。
データ統合に欠かせないShared Data Extensions
複数ブランドをまたいで同じ顧客を把握するには、Shared Data Extensions(SDE)の活用が不可欠です。これを使えば、共通の顧客データを複数のBUから参照でき、横断的な配信制御も可能になります。
逆に設計を誤ると「同じ顧客にブランドAとBから同日にメールが届く」「退会済みの顧客に別ブランドから配信してしまう」といったトラブルにつながりかねません。特に月間配信件数が数十万件規模の企業では、こうした事故が顧客の信頼を大きく損なう要因になっています。
SDEは強力な仕組みですが、どこを共通化し、どこをBUごとに切り分けるか。そのルール作りが、統合運用の成功を左右するといえるでしょう。
ブランド統合で変わる3つの運用設計ポイント
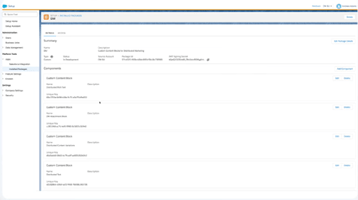
複数ブランドを一つの基盤に統合するとなれば、アカウントを整理するだけでは十分ではありません。運用フローや権限設計、データの管理方法まで見直しが必要になります。
統合直後は「これまでのやり方を変えたくない」と声が上がりがちですが、その姿勢を持ち込むとむしろ混乱を大きくする恐れがあります。ここでは、ブランド統合で必ず押さえておくべき運用設計の3つの視点を整理しました。
権限・ガバナンス設計の重要性
複数ブランドが同じ基盤を使うと、操作範囲の境界があいまいになりがちです。配信リストやシナリオ設定の権限を適切に分けておかないと、「別ブランドの顧客に誤配信してしまった」という事態が起こりかねません。
実際、ある小売グループでは権限ルールを後回しにした結果、管理者が30人以上に膨れ上がり、誰も全体を把握できなくなりました。
こうした失敗を防ぐには、早い段階で「誰がどの範囲を扱えるのか」を明文化しておくのが賢明です。ルールが明確なら、現場の迷いも減り、統合後の混乱を最小限に抑えられます。
配信フロー標準化による効率化
ブランドごとに異なる配信フローを持ち込むと、全体効率は大きく損なわれます。Aブランドは「週次メール+LINE通知」、Bブランドは「不定期メール+アプリPUSH」といった形で進めれば、成果を比較することも難しくなります。
すべてを画一化する必要はありませんが、「キャンペーン施策は週1回」「休眠顧客施策は共通シナリオ」といったルールを設けるだけでも効果はあります。指針を持たせれば、担当者の入れ替わりがあっても迷わずに運用できますし、ブランド間での成果比較もしやすくなるでしょう。
データ基盤の一元化と横断分析
統合の最大の狙いは、ブランド横断のデータ活用にあります。ところがブランドごとに管理ルールが異なると、同一顧客を突き合わせる作業で足が止まります。
たとえばAブランドは「会員ID」で管理し、Bブランドは「メールアドレス」で管理しているような場合です。この課題を解決するには、顧客を識別できる共通キーを定め、基盤を一元化することが不可欠です。
あるECグループでは統合の結果、全体の15%が「複数ブランドで購買するコア顧客」だと判明しました。共通基盤を持てたことで、クロスセル戦略に踏み込めた好例といえるでしょう。
マルチアカウント統合に取り組む際の3つの選択肢
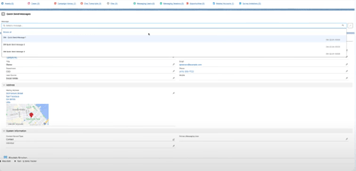
マルチアカウント環境をどのように整理するかは、企業ごとの組織構造や事業展開に大きく左右されます。正解が一つに決まっているわけではなく、あくまで「どの方式が自社に最も合うか」を見極めることが肝心です。
ここでは代表的な3つの選択肢を取り上げ、それぞれのメリットと注意点を整理してみましょう。
単一Org+複数Business Unitによる統合
もっともシンプルなのが、一つのSalesforce Orgに複数のBusiness Unitを置く方式です。全社のデータを一元的に扱えるため、横断的な分析や顧客の重複排除がスムーズに行えます。
特に「グループ内で同じ顧客を複数ブランドが共有している」ケースでは、この方式が適しているといえるでしょう。ただし、BUの数が増えすぎると権限管理やフォルダ構造が複雑化する点には要注意です。
ある大手EC企業では、BUを20近くまで増やした結果、フォルダの階層構造が誰も把握できなくなり、整理に半年以上かかった例もあります。シンプルさが魅力の方式だからこそ、増やしすぎないバランス感覚が求められます。
Multi-Org構成による柔軟な分散管理
次に、複数のSalesforce OrgをMarketing Cloudに接続する「Multi-Org構成」です。地域や事業部が独自のデータ戦略を持っている場合に選ばれることが多く、独立性を保ちながらMarketing Cloudを利用できるのがメリットです。
たとえば北米とアジアで顧客属性が大きく異なるグローバル企業では、Multi-Orgによってローカル最適を実現することが可能になります。しかし、データの重複やシステムの複雑さは避けられず、運用負担は大きくなりがちです。
さらに「複数Orgの統合レポートをどうまとめるか」という新たな課題も生まれます。柔軟性を取るか、効率を取るか。この選択は経営層も巻き込んだ判断になるでしょう。
ハイブリッド型での段階的統合
三つ目は、単一OrgとMulti-Orgを組み合わせたハイブリッド型です。最初からすべてを統合するのではなく、優先度の高いブランドだけを単一Orgにまとめ、その他は段階的に移行していくやり方です。この方法は、現場の抵抗を和らげながら徐々に全体最適へ近づける点で現実的といえます。
実際に国内のある小売グループでは、旗艦ブランドだけを先行して統合し、成果を示したうえで他ブランドを順次巻き込む形を取りました。その結果、関係部門からの合意も得やすく、スムーズな全社統合につながったと報告されています。
ただし「暫定的な二重運用が長引く」というリスクもあるため、ロードマップを明確に描くことが成功の条件になります。
統合設計を成功に導く3つのステップ
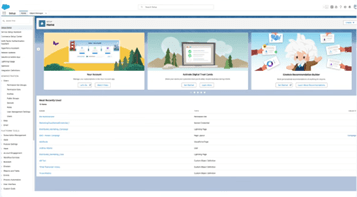
マルチアカウント統合は、システム設計だけで完結するものではありません。組織や人を巻き込む大規模プロジェクトだからこそ、慎重に段階を踏む必要があります。
理想の仕組みを描くだけでは定着せず、現場をどう動かすかが成果を左右します。ここでは実践的に進めるための3つのステップを紹介します。
現状アカウントの棚卸しと課題把握
最初のステップは、現状のアカウント環境を丁寧に棚卸しすることです。
どのブランドがどの目的で使っているのか、配信規模やデータ管理の実態はどうなっているのか。これを把握しないまま統合を始めると、想定外の複雑さに後で気づくことになります。
あるBtoC通販会社では、統合時にリストを突き合わせたところ、顧客の重複率が40%に達していました。この数字が示す通り、現状を洗い出す作業は次の設計に直結する重要な工程です。
運用ルールとデータ設計の合意形成
次の段階では、統合後のルールをどうするかを全社的に決めていきます。権限範囲や配信フロー、データ項目の標準化などは、ブランドごとに意見が食い違いやすい領域です。
「自分たちのやり方を残したい」という声は必ず出ますが、ここを曖昧にすると後で深刻な混乱を招きます。成功する企業は、IT部門とマーケティング部門だけでなく経営層も巻き込み、合意形成のプロセスを重視しています。
確かに時間はかかりますが、運用トラブルを防ぐための最良の投資だといえるでしょう。
導入後の評価指標と改善サイクル
統合は導入して終わりではなく、稼働後に成果を確認し続ける姿勢が欠かせません。配信到達率や開封率、顧客の重複解消率といった指標をモニタリングし、改善サイクルを回すことが重要です。
ある小売グループでは、統合後に「ブランド横断でのリピート購入率」をKPIに設定したところ、1年で横断購入者が20%増加しました。このように指標を工夫すれば、統合効果を社内に示せるだけでなく、次の改善を促すエンジンにもなります。
設計だけで満足せず、走りながら磨いていく姿勢こそ成功の条件といえるでしょう。
まとめ
Marketing Cloudを複数ブランドや事業部で活用する場合、マルチアカウント管理の設計は避けて通れないテーマです。アカウント構造、ガバナンス、データ基盤──これらをどう整理するかによって、統合の成功は大きく左右されます。
本記事では、マルチアカウント管理の基本からブランド統合に伴う運用設計のポイント、さらに代表的な選択肢や実践ステップまでを整理しました。正解は一つではなく、自社の事業戦略や組織の実情に合わせて最適解を導き出す姿勢が求められます。
統合は大掛かりで手間のかかる取り組みに映るかもしれません。しかし、一度基盤を整えてしまえば「顧客接点の一貫性が高まった」「横断的な成果が見えるようになった」といった実感を得られるはずです。全社のマーケティングを俯瞰し、持続的な成長につなげるために、今こそ統合設計を前向きに検討してみる価値があるでしょう。
<Marketing Cloud>
弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!
>>セミナー一覧はこちら
弊社はプロセスコンサルティングを行っている会社です。
お気軽にお問い合わせください!
>>お問い合わせはこちら